【子連れお出かけ】三ツ池公園(神奈川県鶴見区)|アクセス・駐車場・おすすめポイント

こんにちは、カリフォルニアへ帯同予定の研究者妻・Manaです😊
今回は、神奈川県鶴見区にある三ツ池公園を紹介します。
我が家も2ヶ月に1回は訪れる、お気に入りの公園のひとつです。
三ツ池公園の基本情報
三ツ池公園は、3つの池を中心に自然豊かな樹林に囲まれた広大な公園です。桜の名所としても知られ、「さくら名所100選」にも選ばれています。
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区三ツ池公園1-1 |
| 面積 | 29.7ha |
| 入園料 | 無料 |
| 問い合わせ先 | 045-581-0287 |
アクセス
新横浜駅からはバスで約30分、鶴見駅からはバスで約10〜20分です(系統によって異なります)。
「新横浜駅」から
市営バス6系統、104系統の「鶴見駅西口」行きで、「三ツ池公園北門」下車、徒歩約3分「鶴見駅」から
市営バス:JR「鶴見駅」西口、西友前の広場の向かい側「鶴見駅入口」バス停から6系統、67系統、104系統の「梶山」行きまたは「新横浜」行きで、「三ツ池公園北門」下車、徒歩約3分
>横浜市営バスの運行情報(横浜市交通局ホームページ)
臨港バス:JR「鶴見駅」西口バスターミナル、「07系統三ツ池公園経由駒岡車庫行き 又は 同系統三ツ池公園行き」で、「公園正門」下車すぐ
>臨港バスの運行情報(臨港バスホームページ)
駐車場情報
駐車場は正門と北門の2か所にあります。午前中であれば比較的スムーズに駐車できる印象です。
| 利用時間 | 午前5時30分~午後7時30分 (11月1日~3月15日は、午前5時30分~午後5時30分) |
| 収容台数 | 北門駐車場(大型車6台、普通車91台、身障者用2台)、正門駐車場(普通車55台、身障者用2台) |
| 利用料金 | 大型830円、普通510円 ※繁忙期(3/16~4/15、4/29~5/5)は、大型1,250円、普通830円 |
遊具の種類
「遊びの森」には大人気の「ロングすべり台」や大型複合遊具があります。この他にも「ジャンボすべり台」があります。3歳の息子はジャンボ滑り台が1番気に入った様子でした。

ジャンボすべり台は、そのまま滑ることも可能ですが、ヒップスライダーを使うのがおすすめです。
ピクニックにおすすめのエリア
園内には広場が点在しており、ピクニックにも最適です。特に、正門すぐのパークセンター向かいの芝生エリアが人気でした。池の周りでは鯉・鴨・カメなども見ることができます。



キャンプ用テントやタープの使用は禁止されていますが、小型の日除けテントは利用できます。
>「日よけテントご利用について(PDF)」
その他施設
三ツ池公園にはその他の様々な施設があり、自然観察、レクリエーション、健康づくりなど、総合的な魅力を備えています。
パークセンター
休憩スペース、自動販売機、売店などがあります。ジャンボすべり台で使えるヒップスライダーもこちらで売っていました。
運動施設
軟式野球場、多目的広場、テニスコートがあります。利用には事前の申込が必要です。
プール
7月と8月の夏場にはプールが利用できます。最近上の子のおむつが取れたので、この夏は是非利用したいです。しかも、大人310円・子ども110円(1歳から小学生以下)と破格!
売店・キッチンカー
下ノ池のほとりには売店があり、パークセンター近くにはキッチンカー(出店情報はこちら)も来ていました。私はキッチンカーでカフェオレを購入しましたが、本格的で美味しかったです。
まとめ
三ツ池公園は、自然の豊かさ・遊具の充実度・ピクニックのしやすさなど、子連れにとって嬉しいポイントがぎゅっと詰まった公園です。桜の名所として有名なだけでなく、季節ごとの景色が楽しめるのも魅力です。我が家では、ちょっと遠出したい休日の定番コースになっています。都心からは車で40分ほどで、アクセスも良いので、都内からのお出かけにもおすすめです。
Mana🍀
海外赴任帯同中に挑戦したい5つのこと|カリフォルニア生活で実現したい過ごし方

こんにちは、Manaです😊
海外赴任への帯同にあたり、現地で挑戦したいことを整理しました。
今後の生活をより充実させるための備忘録としてまとめておきます。
1. 語学研修への参加
英語力向上を目的に、語学学校やオンラインレッスンを利用する予定です。
日常生活の中でも、積極的に英語に触れる機会を作っていきたいと考えています。
2. Farmer’s Marketでの買い物
健康的な食生活を維持するため、Farmer’s Marketで新鮮な食材を買い、自烈中心の生活を目指します。
現地の雰囲気を感じながら、買い物を楽しめたらと思っています。
3. ヨガやピラティスの再開
津波前に続けていたヨガを再開し、心身のリフレッシュを固めます。
現地コミュニティとの接点を持つ機会としても活用する予定です。
4. プレイデートへの参加
子どもたちに異文化体験の場を提供するため、現地の親子と交流する機会を積極的に作りたいと考えています。
英語に自然に触れる環境を整えることも目標の一つです。
5. 運転免許の取得
生活範囲を広げるため、現地での運転免許取得に挑戦する予定です。
取得に向けた準備も、出発前後で進めていきたいと考えています。
おわりに
今回上げた内容は、帯同生活をより有意義なものにするための目標です。
できる範囲でひとつずつ取り組みながら、経験を積み重ねていきたいと考えています。
Mana🍀
英語でのおすすめ習慣|Three Good Thingsを取り入れてみた
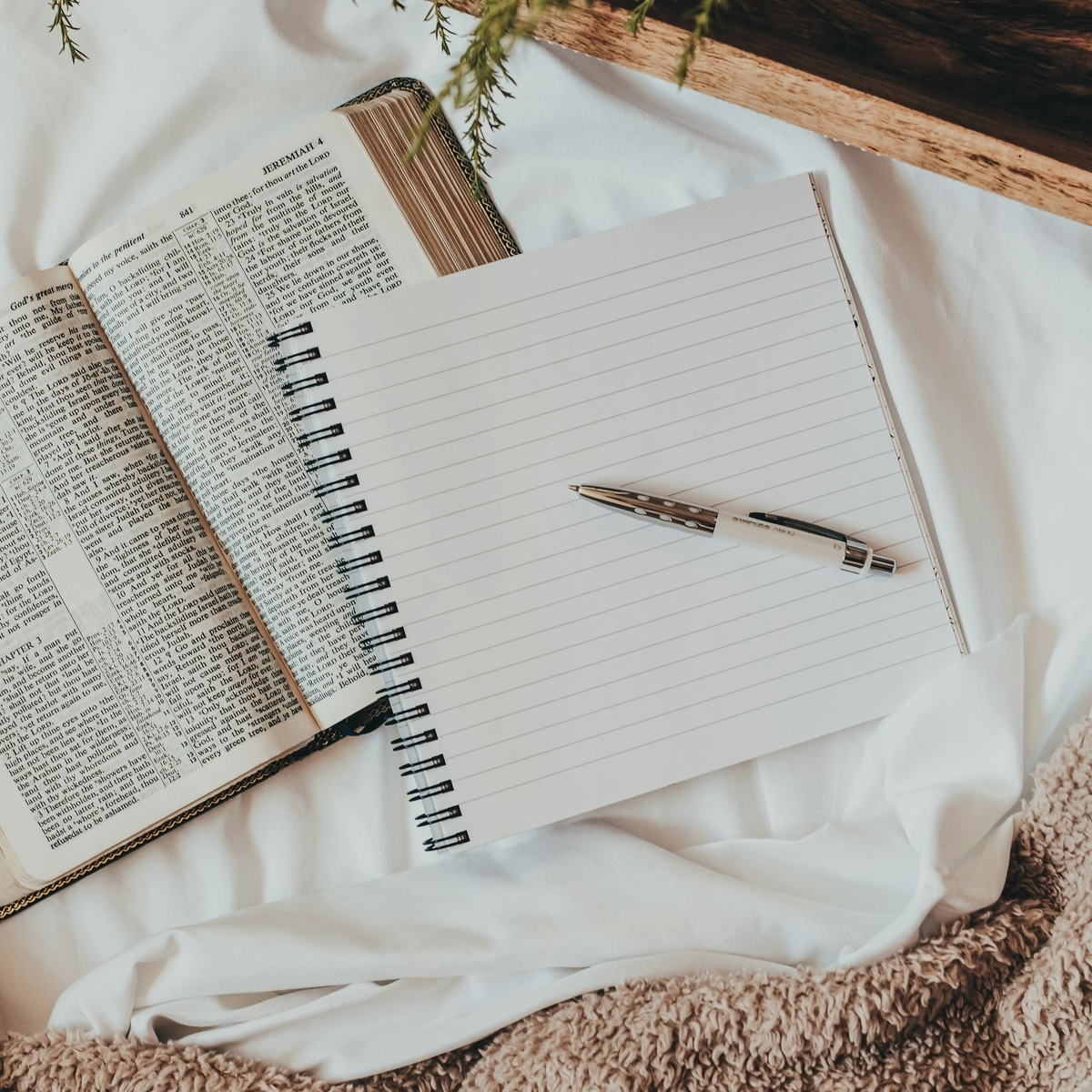
こんにちは、Manaです😊
今回は、私が英語で実践している習慣「Three Good Things(スリー・グッド・シングス)」についてご紹介します。
Three Good Thingsとは?
ポジティブ心理学の第一人者であるセリグマン博士が提唱した、幸福感を高めるためのエクササイズです。やることはシンプルで、「1日の終わりに、今日あった良いことを3つ書く」というものです。
- いつもより早起きできた
- お天気が良くて気分がよかった
- 道に咲いている花がきれいだった
内容は小さなことで構いません。大事なのは、自分にとって“良かったこと”に意識を向けることです。
効果と目的
研究では、幸福感の向上・ストレス軽減・うつ予防などに効果があると言われています。具体的には、以下のようなメリットがあります:
- ポジティブ感情の増加
良いことに目を向けることで、前向きな気持ちが自然と増えていきます。 - ストレスや不安の軽減
忙しい日々の中でも、自分が「満たされた」と感じる出来事を思い出すことで、心が穏やかになりやすくなります。 - 幸福度の向上
継続していくことで、幸福感が持続的に高まるという研究結果もあるそうです。 - 自己理解が深まる
自分が「どんな時に心が動くのか」「どんなことに満足を感じるのか」など、内面への理解も深まっていきます。
なぜ“英語で”書くのか?
Three Good Thingsは本来、日本語でも十分効果がありますが、私は英語学習の一環として、英語で書くことを習慣にしています。
理由は大きく分けて3つです:
- アウトプットの機会を作りたいから
リスニングやリーディングに比べ、ライティングは意識的に取り組まないと習慣化しづらいため。 - 実用的な表現を増やしたいから
自分の言葉で「日常を英語で表現する」ことで、語彙や表現の引き出しを自然に増やせる。 - 気負わず続けられるから
長文を書くのは大変でも、Three Good Thingsは1文×3つで完結するので、負担が少なく続けやすい。
具体的なやり方(3ステップ)
私が実際に取り入れている方法は、以下の通りです:
- 今日あった“良いこと”を日本語で思い出す
- 自分の力で英語にしてみる(わからない単語は辞書)
- ChatGPTに添削してもらい、より自然な表現を学ぶ
例えば、今日の良かったことの1つ「子どもたちがすんなり寝た」を自分の英語で
“The kids slept smoothly”
と表現してみて、ChatGPTに添削してもらうと次のような回答が返ってきました。

とても参考になりますね。ChatGPTを使うことで、表現の幅や自然な言い回しを効率的に学ぶことができます。添削を通して「ネイティブらしい言い回し」も少しずつ身につく感覚があります。
実感しているメリット
この習慣を続けてみて、感じたメリットは以下の通りです:
- 英語を書くハードルが下がった:短文から始めることで、英文を書くことへの抵抗感が少なくなりました。
- 語彙力・表現力が少しずつ増えた:日常の出来事を表現する中で、辞書を使ったりChatGPTの提案を見たりすることで、自然に言い回しを覚えられるようになりました。
- 気分が前向きになれる:毎日を「何か良かったことはあったかな?」という視点で振り返るようになり、ポジティブな気持ちで1日が終われます。また、ChatGPTの添削が優しいので温かい気持ちになります。
続けるコツ
私は、最初から完璧な英文は目指さないようにしています。それこそ、ChatGPTが添削してくれますし。また、できるだけ簡単な単語や短い表現を選ぶようにしています。
あとは、可愛いお気に入りのノートを使ったり、好きなコーヒーを飲みながら書いたりと工夫しながら、無理なく続けることを心がけています。
まとめ
英語学習は、何より継続することがいちばん大切だと思っています。気軽に始められて、気持ちも前向きになれる「英語でThree Good Things」の習慣、おすすめです!
Mana🍀
区立保育園にネイティブティーチャーが来てくれる!?港区の「英語で遊ぼう事業」

こんにちは、Manaです😊
今回は、東京都港区が行っている区立保育園への「ネイティブティーチャー派遣」についてまとめてみます。
ネイティブティーチャー派遣とは?
この取り組みは、港区が行う「英語で遊ぼう事業」の一環として、英語を母語とするネイティブティーチャーを区立保育園に派遣し、子どもたちが自然に英語に親しめる環境をつくることを目的としています。令和6年4月から全区立幼稚園で実施されていましたが、令和7年度からは区立保育園にも拡大されました。
活動の概要
港区が公表している資料によると、事業の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施頻度 | 週2回程度、1回5時間 |
| 対象クラス | 2歳児クラス〜5歳児クラス(実施年齢は各園で決定) |
| 実施園 | 区立の直営保育園 全15園 (芝保育園、芝公園保育園、南麻布保育園、本村保育園、西麻布保育園、麻布保育園、飯倉保育園、赤坂保育園、南青山保育園、青山保育園、伊皿子坂保育園、高輪保育園、白金保育園、こうなん保育園、台場保育園) |
| 活動内容の例 | ・英語によるコミュニケーション活動 ・英語による読み聞かせ、歌や遊戯などの活動 ・給食時の英語によるやりとり、食育活動など |
実際の様子
先日、私の子どもが通っている保育園にもネイティブの先生が来てくれました。子どもに感想を聞くと「楽しかった!」とのこと。帰宅後には、覚えた英単語を披露してくれて驚きました。
同じ園に通うママ友たちからも好評で、
「英語に興味を持つきっかけになりそう」
「習い事に通わせなくても英語に触れられるのはありがたい」
「うちは家庭で英語を話すから、保育園でも英語に触れられるのがうれしい」
といった声がありました。
親として感じたメリットと課題
ちょうど我が家では海外赴任の話が出ていたタイミングだったため、この取り組みはとてもありがたく感じました。
1回5時間 × 週2回 × 4年間(2歳〜5歳)=約1,920時間
これは、英語習得に必要とされる2,000〜2,500時間にかなり近い数字です。通園中にこれだけの英語に触れる機会があるのは、非常に魅力的だと感じます。
一方で、対象は「区立の直営保育園」に限られています。民間委託園(元麻布保育園、神応保育園など)や私立園は対象外です。港区ではもともと直営の区立園の人気が高く、今回のような制度導入により園間格差が広がらないかが少し気になるところです。
まとめ
港区のネイティブティーチャー派遣事業は、英語との“自然なふれあい”を保育園生活に取り入れられる貴重な機会だと思います。このような公的な取り組みがもっと広がっていくことで、子どもたちが無理なく異文化に触れ、言語への抵抗感を減らせるといいなと感じました。
Mana🍀
【配偶者同行休業制度】利用条件・メリット・デメリットをまとめました

こんにちは、Manaです😊
今回は、「配偶者同行休業制度」について、まとめてみようと思います。
私が夫の海外赴任に帯同する際には、この制度を使う予定です。
配偶者同行休業制度とは
配偶者の海外赴任や留学に帯同するために、一定期間休業できる制度です。一部の大企業や、国家公務員、地方公務員などで導入されています。
配偶者同行休業制度について、人事院のホームページには以下のように書かれています。
有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度です。
配偶者同行休業制度の利用条件
民間企業の場合は会社の就業規則に準ずるため、ここでは国家公務員の配偶者同行休業制度の利用条件についてまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象職員 | 一般職の国家公務員(非常勤職員などは除く) |
| 休業期間 | 3年を超えない範囲内 |
| 休業の対象となる 「配偶者が外国に滞在する事由」 |
・外国での勤務 ・事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動 ・外国の大学等における修学 (6ヶ月以上見込みがあるもの) |
| その他の条件 | ・配偶者と現地で生活を共にすること ・給与(俸給・手当)は支給なし ・共済組合・年金など、共済の掛金は支払う必要がある |
配偶者同行休業制度のメリット
- キャリアを継続できる
退職せずに休業できるため、これまでのキャリアを維持したまま海外に帯同することができます。帰国後は制度利用開始前の職務に戻ることができるため、精神的な安心感が大きいです。 - ワークライフバランスが維持できる
配偶者の海外赴任を理由に自身の仕事を諦めることなく、家庭との両立を続けられます。
この制度があることで、家族との時間を選びながらも、将来また働くための土台を残しておけるのは大きな魅力です。
配偶者同行休業制度のデメリット
- 収入が減少する
休業中は給料が出ないため、当たり前ですが収入が減少します。 - 社会保険料を支払う必要がある
共済組合・年金などの共済の掛金を支払う必要があります。無給なのに税金は払わなければいけないのは辛いですね... - 長期滞在は不可能である
国家公務員の配偶者同行休業制度では、最長で3年しか休業できません。民間企業の中には、5年までの休業を許しているところもあるそうです。
感じたこと・気をつけたいこと
私の職場にも配偶者同行休業制度があるため、退職せずに帯同できることに安心しました。一方で、無給になることや、スムーズに復職できるかなどの不安もあります。
勤務先によって運用が異なるようなので、確認は早めに進めたほうが良さそうです。
おわりに
配偶者同行休業制度は、家族の事情に合わせて働き方を柔軟に考えることができるとても良い制度だと思います。私も、これから制度を使って帯同する予定なので、実際に利用した際の手続き方法や感想なども改めて記録していければと思います。
※この記事は、私自身が制度の利用を検討する中で調べた情報をもとにまとめています。実際の運用は所属庁や勤務先によって異なる場合があるため、詳細は各職場の人事担当などにご確認ください。
Mana🍀
研究職の私が海外赴任帯同を決めた理由|キャリアと家族のはざまで

こんにちは、Manaです😊
今回は、「仕事」について少し書いてみたいと思います。
今の私が一番揺れているテーマかもしれません。
子どもの頃から、研究者になるのが夢でした。
第一志望だった憧れの某国立大学に合格したときは、「ここから私の研究人生が始まるんだ」と心が弾みました。
そのまま大学院へ進学し、博士号まで取得。卒業後は研究職に就き、ずっと憧れていた“研究”の世界に身を置くことができました。成果を出さなければいけないプレッシャーなど、大変なことも多かったけれど、私はこの仕事が本当に好きでやりがいを感じていました。
その後、結婚・出産を経て、2人の子どもに恵まれました。
そして昨年、2回目の育休から復帰。
久しぶりに職場に戻り、「またここから頑張ろう!」と前向きな気持ちでいっぱいでした。
でも——
そんなタイミングで、夫の海外赴任の話が舞い込んできました。
「またキャリアが止まってしまう」
ただでさえ産休・育休でブランクがあったのに、また?という不安。
正直、焦る気持ちもありました。
悩みに悩んだ末に、私は「一緒に行こう」と決めました。
子どもたちにとって、家族が一緒に住むことが何よりも大切だと思ったから。
そして何より——
私は夫のことを尊敬していて、そんな彼の挑戦をそばで支えたいと思ったから。
配偶者同行休業制度を使って、一度仕事をお休みすることに決めました。
研究の世界では30代はまだまだ「若手」。遠回りかもしれないけれど、この海外生活は私にとっても必ず糧になると信じています。
英語力を磨いて、帰国後には論文や学会発表など、英語を武器に頑張りたい。
今はそんな目標を持っています。
今は一度立ち止まるけれど、それは未来へつながる準備の時間。
この経験は、きっと私にしなやかな強さを与えてくれると思っています。
Mana🍀
【海外赴任準備】帯同を決めた私が最初にやった2つのこと

こんにちは、Manaです😊
「一緒に行こう!」と決めてから、少しずつ気持ちが海外生活に向き始めました。
今回は、私がまず手をつけた2つのことをご紹介します。
ゆる〜く英語の勉強スタート
まず始めたのは、英語の勉強。
といっても、いきなり教材を買ったり英会話教室に通ったりはしていなくて、できることから少しずつ。無理せず、気が向いたときにできることを少しずつ取り入れています。
- アプリで単語や発音を勉強する
- 朝のニュースを英語番組に変更する
- すきま時間にポッドキャストを聞き流す
こんな感じで、ゆる~く英語学習をスタートして、自分の耳と口を少しずつ英語に慣らしています。
そして子どもたちには、動画コンテンツをぜんぶ英語に変更!
よく観ているNetflixやディズニーチャンネルを、すべて英語に切り替えました。初めは戸惑っていたものの、すぐに慣れたようで、今では楽しそうに観ています。
親も子も、“ちょっとでも英語に触れてる”感があるだけで、なんとなく安心します。
SNS・ブログで情報収集!
もうひとつ始めたのが、SNSやブログでの情報収集。
海外生活の準備を進めている方や、現地で生活している方のリアルな発信を探しています。
たとえば、こんなキーワードで検索しています:
- 「駐在妻 ブログ」
- 「海外赴任 帯同」
- 「カリフォルニア 子育て」
特に参考になるのは、実際にお子さん連れで渡米された方の幼稚園や小学校についての投稿。現地の雰囲気や生活感が伝わってきて、すごくイメージしやすくなります。
調べれば調べるほど、「どんな生活になるんだろう?」と想像がふくらんでいきます。
“ゆる準備”だけど、気持ちの第一歩
こうして書くと、「これって準備?」というくらい、まだまだゆるいスタート。
ゆる〜くでも、心の準備と小さな行動から始めていけたらと思います。
今後の準備も、またブログで記録していきますね。
Mana🍀